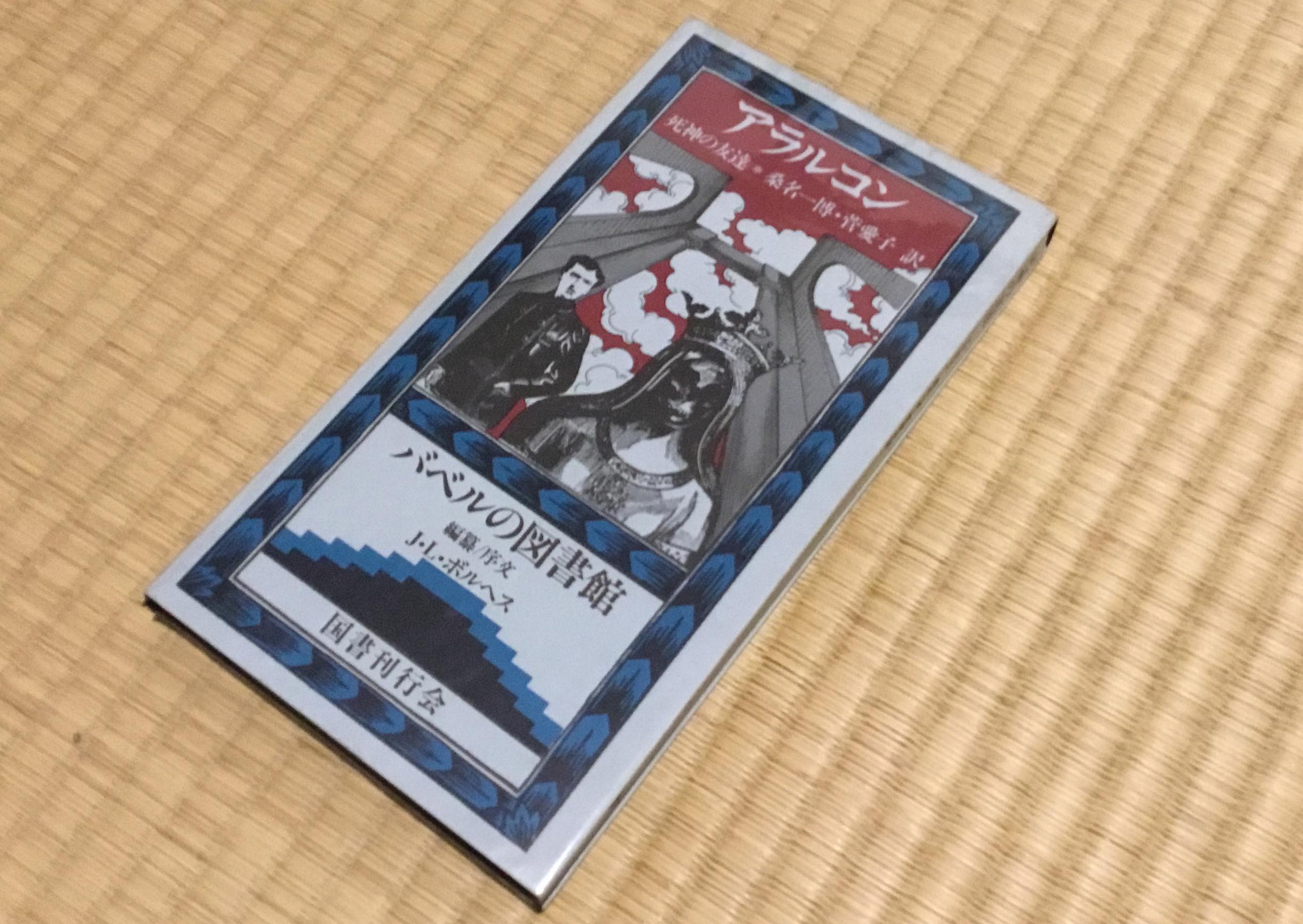アラルコン『死神の友達』(国書刊行会)
記憶をとどめるべく、思い出すままに。
2020年2月9日、「萌えいずる声」が京都国立近代美術館で開催された。
破格のシンポジウムだった、あれほど1分1秒が濃い時間はなかなか無い。終了後にご参加くださった皆様や関係者から伺ったのですが、いびきなどあちこちで鳴る「声」があった。わたしのパートでは最後の最後にまさかの携帯音!仕掛けじゃないかと思われた方もいらっしゃったそうです。これらのことは聴取がいかなるものか、ろう者にとって聴者の体験が突きつけられるものだった。
この企画は昨年の9月に動きはじめ、当日の舞台をつくり上げるために進行のための綿密な資料を作るなど実に多くのプロセスを経ている。前日には手話通訳とビデオチャットをするなど当日にいたるまでイレギュラーなことも含め、緻密なやりとりがあった。おいおい書くこともあるだろう。
当日の舞台裏はてんてこ舞いだった。近美の本橋仁さんと松山沙樹さんは午前のワークショップに出ているため、わたしは牧口千夏さんと準備を進めた。ちょうど、早めにお越しくださった手話通訳がいらっしゃっており、通訳をお願いしながら一緒に準備をする。当日は使えるMacが1台しかなく、百瀬さんの上映用に使用することとなった。わたしのMacをシンポジウム用にするといった設定の変更や機材チェックなどその場で即断しつつ、講堂と控室の行き来をあわただしく繰り返していた。黒嵜さんと岡田先生は手話通訳と打ち合わせに集中していただいた。木下は前日の夜に打ち合わせを済ませていたのが良かった。
わたしはあちこちを飛び回りながら指示を続け、12時半になってようやく弁当を食べる。スタート前の12時40分に全員集合して打ち合わせをする予定だったが、皆さんあちこちの持ち場で忙しく、黒嵜、岡田、木下、手話通訳2名しか集まらずシンポジウムの進行を確認したのち、会場入り。会場は満席。長谷川新さんとすれ違い、会釈をする。彼が京都大学に在学していた時に知り合っており、京都という場で再会できたこと自体は喜びであった。
・上映《聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと》
わたしは中央最前列に座る。百瀬文が隣にいる。百瀬さんの横で作品を見るというのはこれが初めてである。感慨深いという以上にこの瞬間が訪れることを想像すらしていなかった。「木下さん」に届かない声をかけたくなるときだった。しかも、京都というのは、わたしにとって博論のテーマでもあり、思い出深い地である。スクリーニングが始まるまでの緊張と小さな情動。おそらく二度とない感情だろう。
上映後は百瀬さん、黒嵜さん、岡田先生それぞれのプレゼンテーション。本来は、黒嵜さんのあとがわたしだったのですが諸々の事情があり(後日書くだろう)、わたしが最後になった。みなさんの内容、すばらしかった。
以下、受け止めを。
・百瀬文「萌えいずる声によせて」
緊張感溢れる会場。冒頭の司会をされた本橋さんも緊張した表情。百瀬さんは字幕を使いながらプレゼンをされたが、いつものようにはいかないのはさすが。ぎょっとした方もいらっしゃったそう。わたしもこのようなやり方があるのかと思いつつも、百瀬さんが話す表情は、《聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと》からだいぶ遠くなってきたという印象を持った。言い方は難しいが、語りの形式が異なってきている。八重歯がないせいだろうか。面影はあるけれども・・・。百瀬のプレゼンテーションは加藤幹郎が指摘する、サイレント映画とトーキー映画における字幕の定義を超えたものがあるように思う。サイレントでもない、トーキーでもない両義的な字幕。そんな風にみえた。
坂道で百瀬がわたしに思わず声をかけたというエピソードがひとつの核心になっていたが、それを見ると、ファクトとリアリティという歴史学における重要な概念について考えてしまう。その出来事を認識していないからだ。本来ならその空間/時間にいたのだからそこで起きたことを目撃する — ファクトをつかめるはずなのだがそれができなかった。確かにわたしは百瀬と坂道を登ったことから、百瀬のプレゼンテーションからリアリティとして理解することができる。つじつまは合うのだが、ファクトを素通りしてリアリティとして認識している。そんなことが可能なのだろうか?それが身体障害の特性もしくは機能なのだろうか。それがわたしにとっての問題である。
ここから本橋さんから木下に司会を交代。
・黒嵜想「聴者のエラー」
黒嵜さんのプレゼンテーションを拝見するのは初めて。客観的に作品を分析してくださっており、ひとつの地点を得た。百瀬と木下のコミニケーションは最初から「交差していなかった可能性」。百瀬、木下、字幕には「3つの時間」と「3つの物語」があるという示唆には射抜かれた。字幕の位置付けが、わたしにはよく理解できていなかったからだ。また、オレオレ詐欺における受話器からの声や手塚治虫の初期アニメにおけるコマ送りと声優の声の関係性を検討するパートが興味深かった。声と政治の問題はヘゲモニーをキーワードにすれば簡単に落とし込めるが、そうではなく、わたしたちの生活で飛び交う声における帰属の問題があらわにされている。声を認識した瞬間に、その実体をイメージしてしまう。だから「エラー」というと、「失敗」「想定しないバグ」「スリップ」の意味に捉えられがちだが、そうではなく声を聞いた聴者はその声の「根元」というか、声を声たらしめている実体を探し求め、推論してしまうことかと捉えた。この単語について、手話通訳は「エラー」の意味を他の表現に置き換えるのではなく、「エ」「ラ」「ー」と指文字であらわしていたが、見事な解釈だった。
黒嵜さんは百瀬さんの「相槌」について言及されていたが、あの相槌には聾唖の表象性と深い関わりがあるので、それについてもおいおい書いてみたい。それと「ろう者のエラー」とはありうるのか。例えば、手話にはエラーがないのだろうか。これはCGと手話の問題が関係するだろうか。
・岡田温司「「声」とは何か?」
岡田先生らしい、哲学・思想史における「声」にまつわるトピックをひきながら言述する内容。まるで、このシンポジウムの場を調停するかのような語りで、会場にある種の落ち着きが得られたように思う。岡田は、声とはその意味・意図を還元することができないものだという。そこで、わたしの関心をとくにひいたのは「スペキエース」から「スペクルム」(鏡)への言及である。スペキエースはアガンベンも言及しているが、空中に浮遊している薄皮のようなものである、と岡田はいう。
ろう者への教育においてとりわけ重要なアイテムが鏡である。口話教育における発音練習で口の動きを見ながら発声するが、鏡を必要とする。そうして口の形を覚える、というのが目的だとされているからだ。鏡を使わないと自分の口の形が見えないから・・・ではない。そうではなく、鏡を使わなければ自分の声を剥がすことができないからである。岡田は「声と顔の近さ」「声の身体性」といっていたが、それはろう者からすれば鏡を見るとき、自分の顔はすぐ近くにあるようにスペクルムがあってこそではないだろうか(ここで重要なのはマヤ・デレンの映像ではないか?)。化粧する女性の姿からも明らかなように、自分の顔のディテールがよく見える。だから、スペキエースからスペクルムへというアガンベン的な理路はすっきり理解できた。そこからペルソナという道を経由していくのは、木下のプレゼンテーションで明らかだろう。このような理論的な系譜を岡田先生の思考から確認できたのは大きいことだった。
・木下知威「聾唖のサクリファイス」
近代の聾者/聾唖者たちが映像を「発見」したときに起きたのは、手話の保護である。サイレントであっても言語を映像のなかに封印できるということだ。そこから何が起きたのか、映画の歴史におけるろう者/唖者の表象を検証しつつ、百瀬さんの作品を分析するプレゼンテーションをした。
1月から本格的な準備を始めたが、当初の題は「百瀬文、あるいはファム・ファタールの化身」だった。ファム・ファタール、運命の女という意で映画ではおなじみのキャラクターだ。このような百瀬とペルソナの関係という構想は早い段階からあったが、そこにいたるまで必要なものが欠けていた。つまりファム・ファタールが核心ではないだろうと。それは何かわからなかったので、《聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと》から一旦離れて近代以降、ろう者の身体が映像メディアとともにあった時から何が起きたのかを丁寧に確かめる作業に集中することに切り替えた。関連する映像や文献を確認してみると、ろう者や唖者が声による発話を獲得するときにカタルシスが起きていることを確認できるが、そこには「サクリファイス(sacrifice)」があるのではないか。要するに、聾唖という話すことのできない状態と引き換えに発話のモードを獲得する過程を聾唖のサクリファイスと定義した。それは一方通行であって、元に戻ることはできない(アガンベンでいえば、インファンティアを通過した状態である)。
また、身体障害を「アフェクション(affection:情愛/疾患/障害/作用)」と定めたが、それは制度・社会・医学的な身体障害という枠を取り払いたかったからだ。知覚する/される身体に近づけた語りをしたい、と。障害とアフェクションの視点で身体障害を捉えることで啓かれる身体について、論文なり発表なりで何かでもう少し目指してみたいところだ。
最後の最後に行ったアラルコン『死神の友達』のラスト・シーンの朗読で、まさかの携帯音!声の神のいたずらだろうか?この朗読では、スライドに文章を映し出していたが、わたしはその通りに朗読していない。
・シンポジウム
非常に多岐にわたる話が展開された。わたしはチャップリンの「サーカス」における綱渡りのシーンを引き合いに、ろう者にとって声とはアクロバティックなもので、緊張感を強いるものだと述べた。シンポジウムで岡田先生も話されていたが、黒嵜さんと共鳴する部分が多かったように思う。司会としてはもう少し対立軸を作り、声への思想を広げたいと思っていたが、調和ではなく、ぶつかり合いをしたかった。このあたりは宿題かなと思っている。最後に、黒嵜さんと舌について話が広がりそうなところで終了。
思いついたが、話せなかったことについていくつか。年末の紅白で美空ひばりが「復活」し、歌うあの身体である。それには舌が存在しないことが重要だ。ひばりが口を開けばそこは暗闇、空洞だ。声の「主」の不在がよく示されている。わたしからすれば、あの身体には声がないのだ。しかしながら、初音ミクやアレクサには舌はないが声はあると思える。それはおそらくハイデガーが使う「ダーザイン」が関与するのではないかという予感がする。つまり、身体の実存が声の有無を定めているのではないか。
また《聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと》と京都の関係も重要だろう。この作品を京都で上映することの意味はおそらく、京都盲唖院における聾唖教育の発音訓練と関係する。それに、盲唖院に入らなかった聾唖者の声にならない声を伝える新聞記事。これらとの検討を経ることで歴史的な布置も示せるだろう。書く機会があればやってみたい。
裏側では手話通訳・文字通訳が動いていた。それについての会場からの感想も少なくなく、このシンポジウムの強度を高めるものであったことは間違いない。なによりも会場には遠くからいろんな方がお越しくださっており、嬉しかった。すばらしい時間を岡田先生、百瀬さん、黒嵜さん、近美の皆さん、参加してくださった皆さんと作り上げることができた。
皆様、どうもありがとうございました!またどこかでお目にかかれましたら嬉しいです。